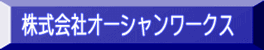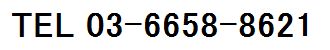管路内特殊調査工
平成23年3月の震災以来、下水道の管路内調査が以前にも増して重要な項目となりつつ有ります。
又、東京では昭和30年頃、周辺都市でも昭和40年頃に急速に建設された下水道管が耐用年数を大幅に超えつつあります。 弊社で調査を実施した路線でも様々な損傷が発生しております。
それらの状態を把握し、健全な下水道運営を行う為に通常の管路内調査に加えて、特殊調査の実施が必要ではないでしょうか。
実際に、構築されてから一度も管路内の状況を調査していない路線が数多く有ると聞き及びます。
人孔間の距離が長い 水位が高い 流速が速い 酸欠やガスの危険性が高い
等々、一般作業員で行うには危険性の高い状況での目視調査を潜水士によって実施します。
管路が完全に冠水している伏越管渠やサイホン管の堆積調査等も潜水士によって実施します。
調査内容
1.東京都下水道局管路内調査工標準仕様書に基づく調査を(堆積調査含む)行います。
2.延長距離が長い場合でも異状箇所以外に管路内状況が把握出来る様に、状況が許す限り、
50m間隔以内で写真撮影を行います。
3.管路のコンクリート強度試験をシュミットハンマーで行います。
4.流速及び距離に制限はありますが、コア採取も行います。
5.水中部はクリアサイトを使用してコンクリートの状態等の撮影が可能です。
6.コンクリートの中性化測定を行います。(水上部)
7.ビデオ撮影を行います。
8.管路内の流速を測定します。(電磁流速計)
調査範囲
管路内の状況(主に水位、延長距離、流速)に依って左右されますが、内径は1,000㎜から、流速は秒速2m程度迄目視調査可能となります。又、完全に水没した満管の場合でも上下流からそれぞれ500m、合計1,000m程度まで調査可能です。
コア採取は管の内径が1,800㎜程度から可能となります。。
調査器材
水位、流速、管径、延長距離、ガスの発生状況に依って変化しますが、次の3種類の器材を基本にして組み合わせを変化させて対処します。
① 『圧縮空気ボンベを携帯』
(1)4リットル 19.6MPa.5.6kg⇒約20分連続呼吸可能
(2)11リットル 19.6MPa.13kg⇒約55分連続呼吸可能
② 『地上からの圧縮空気をホースを介して送気呼吸』
(1)低圧コンプレッサーを使用⇒連続呼吸可能時間の制限無し
(2)圧縮空気ボンベを使用⇒用意した本数の連続呼吸可能
③ 『②を基本にして緊急用に圧縮空気ボンベを携帯』
作業例
 呼吸器を使用した管路内調査の装備例です。
呼吸器を使用した管路内調査の装備例です。
 調査距離が長い場合は途中に補助の潜水士を配置します。
調査距離が長い場合は途中に補助の潜水士を配置します。
 ほぼ満管の管路に予備の呼吸用ボンベを装備して進入します。
ほぼ満管の管路に予備の呼吸用ボンベを装備して進入します。
 本管調査の様子。
本管調査の様子。
 エアー工具で壁面を斫り、中性化試験をします。
エアー工具で壁面を斫り、中性化試験をします。
 コアマシーンを使用してコア抜きをします。管の内径1800mm程度から対応可能です。
コアマシーンを使用してコア抜きをします。管の内径1800mm程度から対応可能です。
 シュミットハンマーを用いて壁面の強度調査をします。
シュミットハンマーを用いて壁面の強度調査をします。
 携帯型の電磁流速計を用いて流速を計測します。
携帯型の電磁流速計を用いて流速を計測します。
 管路内のクラック等に止水パテを塗布しています。
管路内のクラック等に止水パテを塗布しています。
 管路内の堆積調査です。道具が多い場合はゴムボートで荷物を運搬します。
管路内の堆積調査です。道具が多い場合はゴムボートで荷物を運搬します。